ポケットビリヤードでは、手球のNEXTを「どこに」「どうやって」出すのか・・・?
今回は、手球の「出し」、ポジショニングについて、そのコツや考え方を説明します。
ビリヤードを始めてある程度のシュート力が身につくと、次に身につけるべきは手球のポジショニングテクニックでしょう。
ゲームに勝つためには不可欠な技術だし、同時に発展途上の人にとっては上達への壁でもあります。
ってか、おいらは未だに悩むことが多いです・・・^^;
で、ポジショニングするにしても、「どこに」「どうやって」という基本的な考え方ができないと先へ進めないと思うんです。
そこのところを、おいらなりに説明しちゃおうというわけです♪
スポンサーリンク
どこに手球を出すべきか?
まずは、
手球をどこに出すべきなのか?
ということが分からない場合に、何を判断基準にすればイイのかという話からです。
まだ3手先、4手先・・・まで考えられない状態だったら、
『狙えるポケットが多い(選択肢が多い)エリア』
を選ぶことをオススメします。
どういうことかって言うと・・・
ちょっと極端な例ですが、下図のような状況で、AとBのどちらの方向に手球を出すのがベターかという話です。
3番ボールを右下コーナーへポケットして、4番ボールを狙える位置に手球を出します。
A、B、どちらの方向へも、ヒネリを使わずに上下の撞点の使い分けだけで持って行けそうな配置ですね。

で、A方向に出すと、4番ボールを直接狙えるポケットは画面下のサイドポケットだけです。
しかも、そのためのNEXTゾーンも限られた狭い範囲だけ・・・。

でも、B方向に出すと、直接狙えるポケットは3ヶ所になり、その分、ポジショニングできる範囲も広くなります。

Aの場合だと、画面下のサイドポケット1点狙いの出しになりますよね。
ショットが強すぎたり弱すぎたりしたら行き詰まることにもなるでしょう。
それに対して、Bの場合ならポケットの選択肢が多いから、次の5番ボールに出す際にも都合が良いと思うわけです。
でも、実践の場では往々にしてAを選んじゃったりして・・・。
そういう人って、
無意識で自分が苦手なショットを避けていたり、
「もう次はこのポケット」って決めつけちゃって、ほかの選択肢が目に入らない、
みたいな感じなんでしょうね。
でもテーブル上をよぉ~く観察してみましょう。
きっとよりべターな場所、方向が見つかると思います。
要は、どちらがリスクが少なくて効率的なのかって話です。
確かに、「ここしかない!」っていう場面はあるけど、
「ここじゃなきゃダメ!」っていうルールはないわけです。
でも、「これがベター♪」っていう考え方もあるわけですね。
こうやって、リスクや効率を考えればNEXTが見えてくるんじゃないかなって思います。
上手になってくると、的球に対する「フリ」ってヤツを考えながらポジショニングするようになります。
でもこの解説では、あえてまだ詳しく触れていませんよ。
スポンサーリンク
どうやって手球を出すべきか?
手球の“細かぁ~い”ポジショニングには、どうしてもヒネリを使う頻度が高くなると思います。
ま、ヒネリについては頑張って練習してもらうとして・・・
今度は、
「どうやって手球を出す(ポジショニングする)か?」
という点について語っちゃおうと思います。
■まず1つ目のポイント♪
「ここに出したい!」っていうNEXTゾーンが決まると、そのために手球を走らせるコースとして、複数の候補が挙がる場合がありますよね?
そんなとき、理想的なのは、
『手球の自然な動きを利用して無理なく出せるコース』
を選択することだと思うんです。
つまり、“極端な”ヒネリやハードショットを使って、手球を強引にコントロールする必要があるコースは選ばないでって話です。
これもまたリスクや効率の話につながります。
例を挙げるのが難しいんですけど、下図のような場合かな・・・。

かなりフリの小さい配置なので、こんなふうに出そうとしたら、けっこうなハードショットになりますよね?
そうなると撞点だってズレるだろうし、ポケットから吐き出されちゃう可能性だってあります。
なので、下図にようにポジショニングすれば、まだ自然じゃね?って話です。
多少逆ヒネリを使うことになるけど・・・。

■そして2つ目のポイント♪
これ、おいらの持論なんですけど・・・
『できるだけ、NEXTゾーンに沿うように手球のコース取りをする』
つまり、
『NEXTゾーンを横切らない』
ということです。
あくまでも“できるだけ”・・・ね♪
さっきの図で説明すると・・・
前者はNEXTゾーンに対して、ちょっと「横入り」するコースですよね?
でも後者はNEXTゾーンに対して縦に入ってくる、すなわちゾーンに沿って入ってくるコースです。
「横入り」するコースだと、手球の移動距離が長すぎたり短すぎたりした場合の影響を大きく受けます。
次の的球に対する狙い(厚み)が、薄くなっちゃったり、「くの字」になっちゃったりして・・・。
でも、最初からNEXTゾーンに沿って縦に入るコースであれば、多少距離が長くても短くても、次の的球に対する配置はあまり変わりませんよね。
これ、理想だと思うんですよ♪
あ、もちろんこれも、「こうするしかない!」って場面はあるけど、
「こうしなきゃダメ!」っていうルールはないわけです。
でも、「こうするのがベター♪」っていう考え方はあると思うんですよね。
これまた、リスクや効率を考えた場合の、あくまでも「理想のお話」ではありますけど。
スポンサーリンク
慣れてきたら3手先まで考えよう!
以上のように、
「リスクや効率を考慮したポジショニング」
が理解できるようになって、手球のコントロールもある程度思うようにできるようになってきた・・・。
そしたら、よく言われる、
『NEXTは、最低でも3手先まで考える』
ってヤツを実践しましょう♪
どういうことかって言うと・・・
1番ボールから、2番、3番、4番ボールという順に取り切る場合、
① 4番のここに手球を出したいな・・・
② そのためには3番のここに手球を出さなきゃな・・・
③ だとすれば2番のここに手球を出しておくべきだな♪
というように、逆算的にポジションを考えた上で、まず目の前の1番ボールに挑むわけです。
例として図に表すと、下図のような感じです。

これらの一連の考え方を『組み立て』って言います。
的球を1個ポケットするたびに、
2番ボールから、3番、4番、5番ボールまで、
3番ボールから、4番、5番、6番ボールまで、
というように、少しずつ組み立てを修正しながら、最終的に9番、10番ボールまで取り切るというイメージです。
組み立てを考えるには、それぞれの的球に対する手球の配置、とくに『フリ』を考慮しなければなりません。
手球をあっちに持っていくためには、ここにあるとやりやすい・・・
そう考えるだけのことなんですが、思ったとおりの位置に手球をコントロールするのが難しいわけですよね。
でもね、上級者だって、毎度毎度パーフェクトには行かないんですよ。
往々にして途中から組み立てを考え直す(リカバリーする)ことになるんです。
その際には選択肢が多い方が便利♪
ってことで、さっきの、
「リスクや効率を考慮したポジショニング」
という考え方が活きてくるんですね♪
慣れてくれば、簡単な配置ならパッと見ただけで頭の中に組み立てが浮かぶようになります。
がんばってください♪
スポンサーリンク

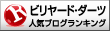
















この記事へのコメントはありません。